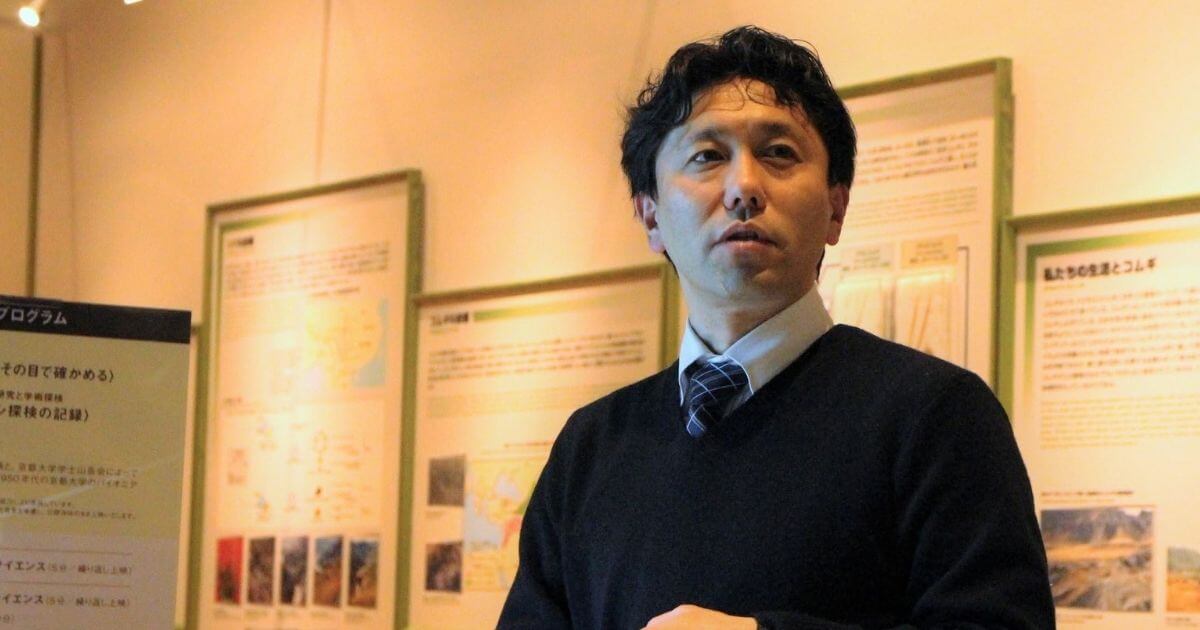ふたつの家族が、「無い」から作った小さな学校。福岡県・糸島のフリースクール 「産の森学舎」がつくる学校のかたち

教育機会確保法が施行されて4年。学校外の学び場が認められるようになり、フリースクール等の存在は重要視されている。
多種多様なフリースクールがある中で今回話を聞いたのは、福岡県西部の糸島市に校舎を構える「産の森(さんのもり)学舎」の理事長・小学部校長の大松康さん。
6年前に設立された産の森学舎は現在、小学生、中学生を合わせて26人の生徒が通う小規模な学び舎だ。ワークショップ形式の授業をメインに、中学部では生徒の自由な探究学習も行っている。
学びの多様化が進む今、フリースクールは必ずしも不登校児童生徒だけの選択肢ではない。フリースクールという立ち位置で、どのように子どもに寄り添い、教育に向き合っているのかに迫った。

「もじとかず」「英語」の授業を担当
福岡市出身。高3の夏から1年間、米国ミシシッピ州に留学。慶應義塾大学総合政策学部卒業。 娘のアレルギーがきっかけで生き方を問い直し、 3年半勤めた監査法人を退社。2008年糸島市に移住し、自然農農園で研修。長女が小4、長男が小1になる年に妻、友人夫妻と共に産の森学舎を開校。年末年始は杵つき餅屋を営む。
「無い」「足りない」だから「作りたい」
——まずは大松さんが「産の森学舎」に携わるまでの経緯を教えてください。
もともとは東京の監査法人で働いていましたが、13年前に福岡に帰郷しました。
東京にいた当時、2歳だった娘のアレルギーがひどくて、食べ物や身の回りのものにすごく気を遣うようになったんです。自分の仕事も肌に合わないと感じていた頃でもあったので、地元の福岡に戻り農業を始めようと、この糸島にやってきました。
その後は娘のアレルギーのこともあり、子どもの育つ場にこだわりたいと考えるようになりました。娘が通う歳には間に合いませんでしたが、妻が届出保育施設「みつばちおうちえん」を11年前に開園しました。
——娘さんのアレルギーをきっかけに、どこで過ごすかを気にされるようになったんですね。
娘が年長になると、次は小学校のことを考えるようになりました。国内外のさまざまなスタイルの学校を調べたら素敵な学校はたくさん見つかったのですが、残念ながら自分たちの住む糸島では選べない。
親として「自分の子どもにどういった子ども時代を過ごしてほしいか、今後どういう学びの中で大きくなってほしいか」を考えた末、6年前に産の森学舎の立ち上げに至りました。
立ち上げ前の構想期間4年の間に、仲間を募ったり、さらにフリースクールや教育思想を勉強したり、どんな形でフリースクールが運営できるかいろいろ試しました。
現在は、同じくらいの年齢の子どもを持つ家族と私たちの2家族が、法人の運営に関わっています。うちの子どもたちもこの学舎で学んでいます。

——「産の森学舎」の設立にはどのような思いがあるのでしょうか?コンセプトにしている「くらし」「あそび」「学び」についても詳しく聞かせてください。
まず私たちはアンチ公立校ではなくて、「いろいろ選べる」形がもっと広がるといいなという思いが大前提としてあります。子どもが多様なのだから、学びの場の多様性が非常に重要になると考えています。
産の森学舎の設立前、娘が通っていた保育園の園長が「引き算の保育」とおっしゃっていて、その言葉がすごく好きだったんです。思い返せば、その保育園は泥と水と高い所があって、体をしっかり動かして、大人が優しく声をかけているというシンプルな環境でした。
足した後に引くのはすごく難しいですよね。「無い」「足りない」だから「作りたい」と子どもたちが思える環境を創りたいと考えたのが根底にあります。そんな「引き算の学校」を目指して、行き着いたのが今のコンセプトです。
産の森学舎のある地域が素敵なところで、目の前に海、振り返ったら山、隣にはアユが泳ぐ川があるんです。そんな豊かな自然に寄り添う暮らしと、子どもたちの内から湧きあがる遊びが充実すれば、必要な学びはきっとそこにある。
そうして「くらし」と「あそび」と「学び」をひとつながりにするというコンセプトが生まれました。

——素晴らしい環境ですね。
産の森学舎は、自由を実現するためにどうしたらいいかを考えて試せる場にしたいと考えています。
例えば「ゲームやおもちゃなど何でも持ってきて良い」とはしていません。ただ「手づくりの物ならOK」と伝えています。
そうすると、市販のカードゲームにハマっている子どもは自分で厚紙を切って作るんです。作っているとだんだんとオリジナルのカードも増えていく。それはもうただ買ってきたものとは違いますよね。
そうやってできる限り子どもを消費者にしない場づくりを心掛けています。何かが無いこと、足りないことに不満を抱えるのではなく、動機にしてもらえたらなと。

大人は、子どもという「森」の「鳥」でありたい
——大人のスタッフが子どもとの関わりで大事にされていることはありますか?
学校を作る上で、「そもそも学校って何だっけ?」という問いに戻って学校をデザインしました。私たちの結論として出てきたのは単純に「大人と子どもが一緒に暮らす場所」。
そこに大人がいる意味は何だろうか、子どもではない人がそこにいることはどうして重要なのかと考えたときに、大人の人生や経験、好きなことがこの学校に反映されることが一番自然なのではないかと思いました。
私たち大人は、「種を運ぶ鳥」のような存在だと考えています。

——種を運ぶ鳥、ですか?
よく子どもは種で、お水を与えて芽が出て枯らさないように……と例えられますが、子どもってもっと逞しいものだと思うんです。森の中には芽が出ていない種もいっぱいあるんですよ。かと思えば更地だったところに勝手に植物が茂ったりする。
森を育てる植物の種がどこからやってくるかというと、風に運ばれたり、鳥が食べた種が糞として落とされることで種が蒔かれますよね。鳥が糞をして、糞に紛れた種が適地から芽吹いて、木が生える。
そうやって森が広がっていくように子どもたちは自分自身を成長させていくと思うんです。言い換えるなら私たち大人がしているのは「鳥の糞」のような役割ですかね。
漢字が好きなスタッフ、美術好きのスタッフ、自然が好きなスタッフがいて、ひたすら糞を落として行く。いつかその種の芽が出てくれたらおもしろいし、芽が出なかったとしても、「昔、漢字が好きな大人がいたな」と思い出になればいい。
試験だと子どもが選ばれる側になりますが、子どもは本来自分が何を学び、どういう生き方をするか選べる「森」のような存在であることを前提に子どもと向き合っています。

——「しぜん」「作家の時間」という特徴的な授業も展開されていますね。授業作りはどのようにされているのでしょうか?
私も小学部で漢字と数の授業を担当していますが、教員の免許は持っておらず、いわゆる教員ではありません。教えるというより、漢字と数が大好きな大人が「大好き」をシェアする時間として授業の時間を担当しています。
漢字の授業では、漢字辞書を使いながら「体の部位の漢字」「漢字一文字の動物」のようないろいろなテーマで漢字ビンゴを作ったり、子どもたちの名前に使われている漢字の由来の独自の解釈を紹介したりしています。
成り立ちや説明も辞書ごとに違うので、比べたり考察したり、覚えることだけに捉われずに漢字と仲良くなってもらいたい。その過程で子どもたちは辞書の引き方を覚えて、他の授業や遊びの中で辞書を使うようになったりします。
例えば「作家の時間」。作家の時間にでは子どもが書きたいことを書きたいジャンルで書きます。毎週短編物語を書く子もいれば、何週間もかけて長編物語を書く子もいます。当然最初はひらがなだけの文章ですが、だんだん文中に漢字がほしくなるようです。
海賊の物語を書いている子は、辞書を引いて「海賊」という漢字を調べる。そうやって自分の世界観に必要な漢字がどんどん増えていくんです。
「教わっていないから書けない」ではなく、「何か書きたい」というモチベーションから「漢字がある方が読みやすい」「もっと漢字を書きたい」という学びにつながっていく感覚です。授業間で内容が近づいたり補完し合うことはたびたびあります。
また、「しぜん」の授業は、自然に関するワークショップやライターの活動をされている方が担当しています。
周囲の自然を教材にして生き物を観察したり、自分たちで椿油を種から絞り川で釣ったえびを揚げて食べたり、つる草を取ってカゴを編んだり、野草茶を作ったり、毎回楽しそうです。

——子どもが物事に直に触れ、経験を通して学ぶ環境があるんですね。子どもの学びという観点で印象的なエピソードはありますか?
以前、魚が大好きな子がいたんですよ。とにかく魚が好きで、部屋の大きさはここからここまでが何メートルっていう話をしたら、「ジンベイザメと同じぐらいだ」と返すような子でした。何を聞いても魚のことは知っているし、日記にはいつも魚の絵を書いてました。
「魚が好き」って、教科でいうときっと「理科が好き」になるんですよ。もちろん生物のことが好きだから。でも彼は魚が好きだから、魚が出てくる物語が好きだし、魚の歌も好きだし、魚の絵を書くのも好きだし、魚の数を数えるのも好きなんです。
だから彼の「魚が好き」っていうところをハブにして、いろんな世界につながれるんですよね。「魚に関しては理科で学びます」というのは、彼にとってもったいないことだし、全て魚に引き寄せた方が理解も早い。実際にそういうことを彼から学びました。
どんな世界でも自分の好きなものにたぐり寄せたり、そのための手助けをしてあげるだけで、あるいはその世界を一緒に歩くだけで、彼らの世界が広がるんです。

子どもを消費者にしない教育を
——教科学習で学習する内容は、何かを学ぶ際の基礎になることも多いです。フリースクールという選択肢が見えたときに教員や保護者の方が不安に感じるところでもありますね。
インプットしたものをいかに早く正確にアウトプットするか、それが得意だったり苦手だったりすることと、本来の学びは別物という気がします。逆にテストなどで身についてしまった苦手意識を払拭するのはかなり大変。勉強って究極的にはテストのためのものではないですよね。
やらされるのではなく興味関心が原動力になっていると、普段はテストや宿題のない産の森学舎の子どもたちが「テストしてくれ、宿題くれ」と言うことがあります。「学びたい」という感情が子どもたちからあふれてくるかが、学力という意味では重要なんじゃないかなと考えています。
本来は「知らない」ってすごく宝物。子どもたちは知らないから知りたいし、分からないからこそ方法を模索したり、チャレンジしたりできる。「知らない」「分からない」がすごく重要だと思うんですよ。
もっと子どもの「知らない」や「分からない」に対して、大人は敬意を表する必要があると感じてます。子どもたちには自分の「知らない」「分からない」の可能性にワクワクしてほしいから。
そうやって彼らの学びが自立していくことが、彼らの学びの土台になると信じています。

——フリースクールと学校の未来について聞かせてください。今後、既存の学校とどのような関係性を築いていきたいと考えますか?
ときどき視察として校長先生が産の森学舎の普段の様子を見に来られることもあって、「素敵なところですね」と言ってくださいます。
高学年になり、国語や算数といった教科学習に興味を持ち始めた子どもたちに、学校が学習用のプリントを用意してくださることもあり、子どもたちが大変喜んでいました。
学校にも、フリースクールにも、それぞれの固有の課題はあると思います。一人ひとりの子どもがやりたいことを実現するため、その子が進みたい道のために、学校とフリースクールがお互いの活動をフォローし合っていければ良い関係かなと考えています。
——子どもがフリースクールに通うことをどう扱ってくれるかは在籍している学校や地域によって違いますよね。
そうですね。実際に産の森学舎に通っている子どものほとんどは、出席扱いを認めてもらえていません。特に中学生になると、出席扱いにならないことが高校進学にも響いてくるので、子どもたちにとって不利な状況です。
出席扱いをされることって、フリースクールが必要な子どもがいること、彼らにとってフリースクールが大切な学びの場であることを認めてもらうことだと思うんです。それがまだ一般的ではない状況がすごくもどかしいですね。
子ども自身が公立学校に戻りたいという思いを持ったときには当然それをサポートしますが、フリースクールが一時しのぎではなく、大切なホームとなりえるということを知ってもらいたいです。

ことを知ってもらいたいと語る大松さん
——ここ数年で、教育機会確保法も含め、学校教育の中でも制度の変化が進み始めたように感じます。今後こうあってほしい教育の形、自らが作っていきたい学びの環境像をお聞かせください。
「子どもを消費者にしない」というのがキーワードになると思っています。
フリースクールのニーズは増えていて実際に問い合わせの数も多いです。産の森学舎ではここ数年、常に定員に達していて途中編入の児童をお断りせざるを得ない状況もありました。ニーズに対してキャパシティが足りてないと実感します。
今後フリースクールのほかにも学校外の学び場は増えていくのでしょうが、その際に子どもが好きそうなことを何でも与えたり、あれもこれもやりなさいと詰め合わせて学びを商品として捉えたり、子どもを市場と考えてしまうようなことがない形で、教育の現場が増えていってほしいと願っています。
また、子どもに未来を担わせるのは、大人がきちんと担ってからの話だということを、学び場を作る人が肝に銘じることが重要だと思います。
子どもに未来を変えてもらおうとするのではなく、大人が今ある課題に向き合うこと。その先の世界に送り出してあげる感覚で学びの場を作らないと、結果的に子どもに何でも背負わせる形で、あれもこれもと詰め込んでしまう。
たくさんのことを子どもに課すばかりの環境ではなく、子どもが子ども時代を謳歌できるような学びの場の形を目指したいです。
〈取材・文=末本 晴香/写真=ご本人提供〉