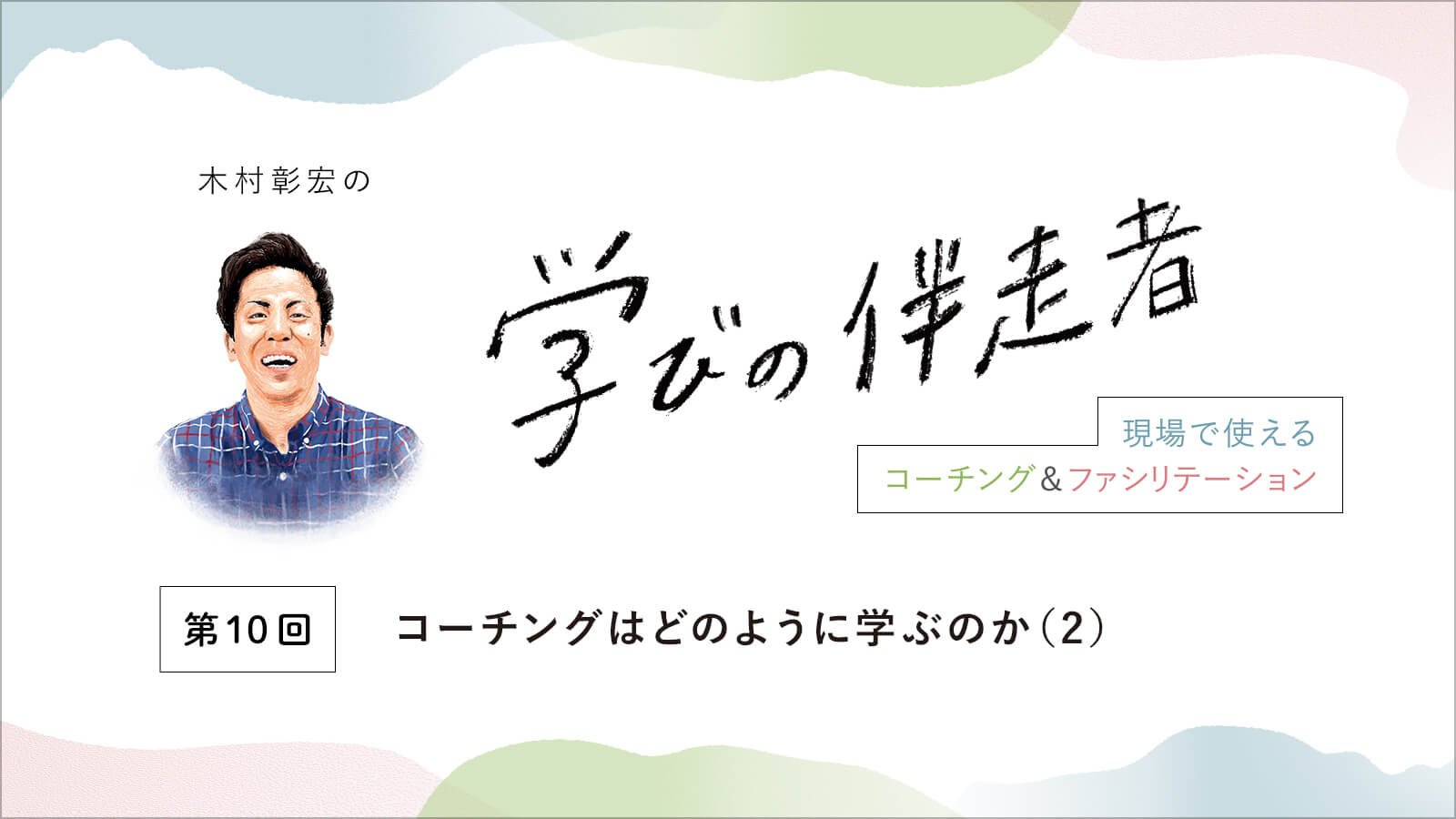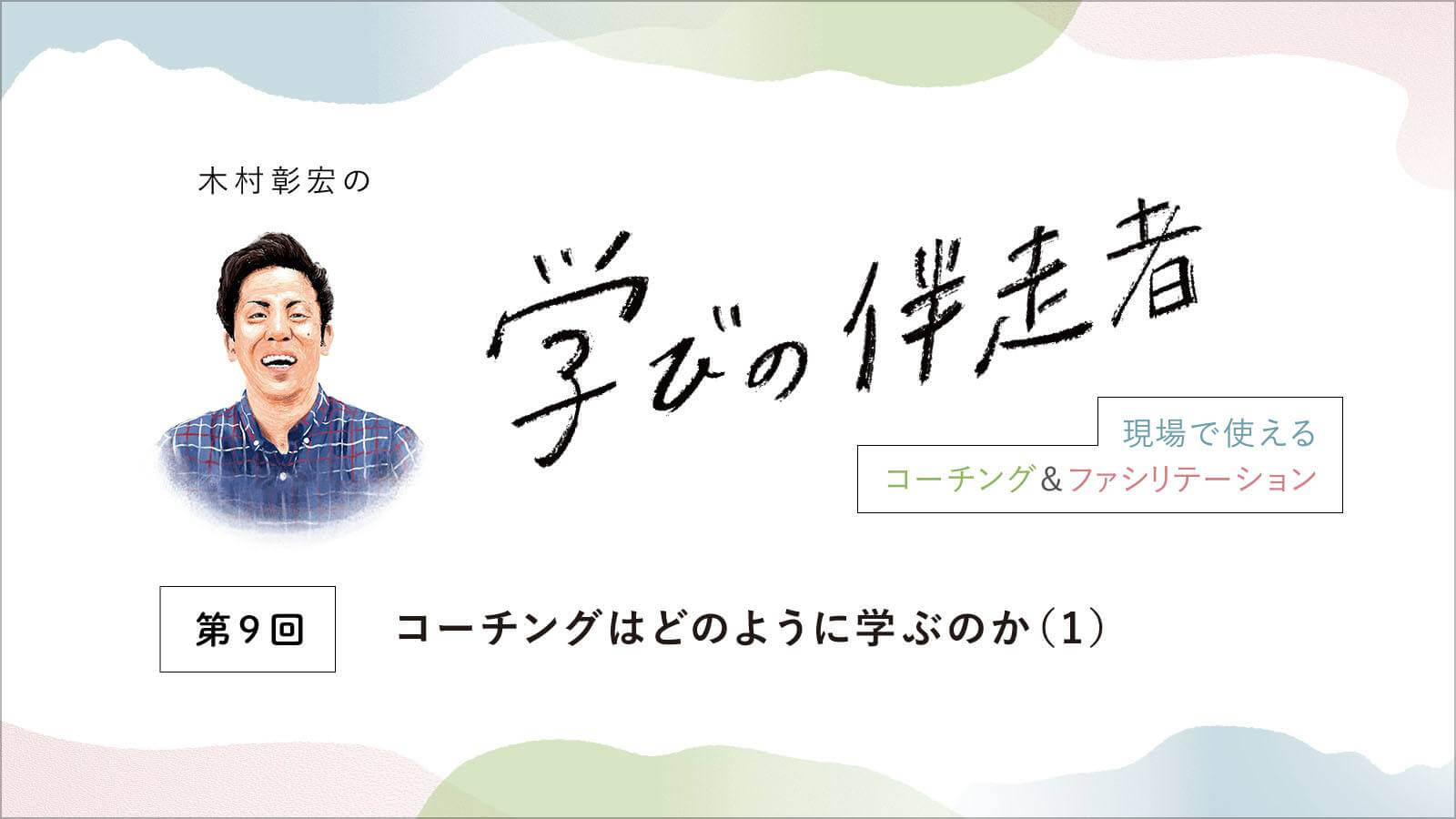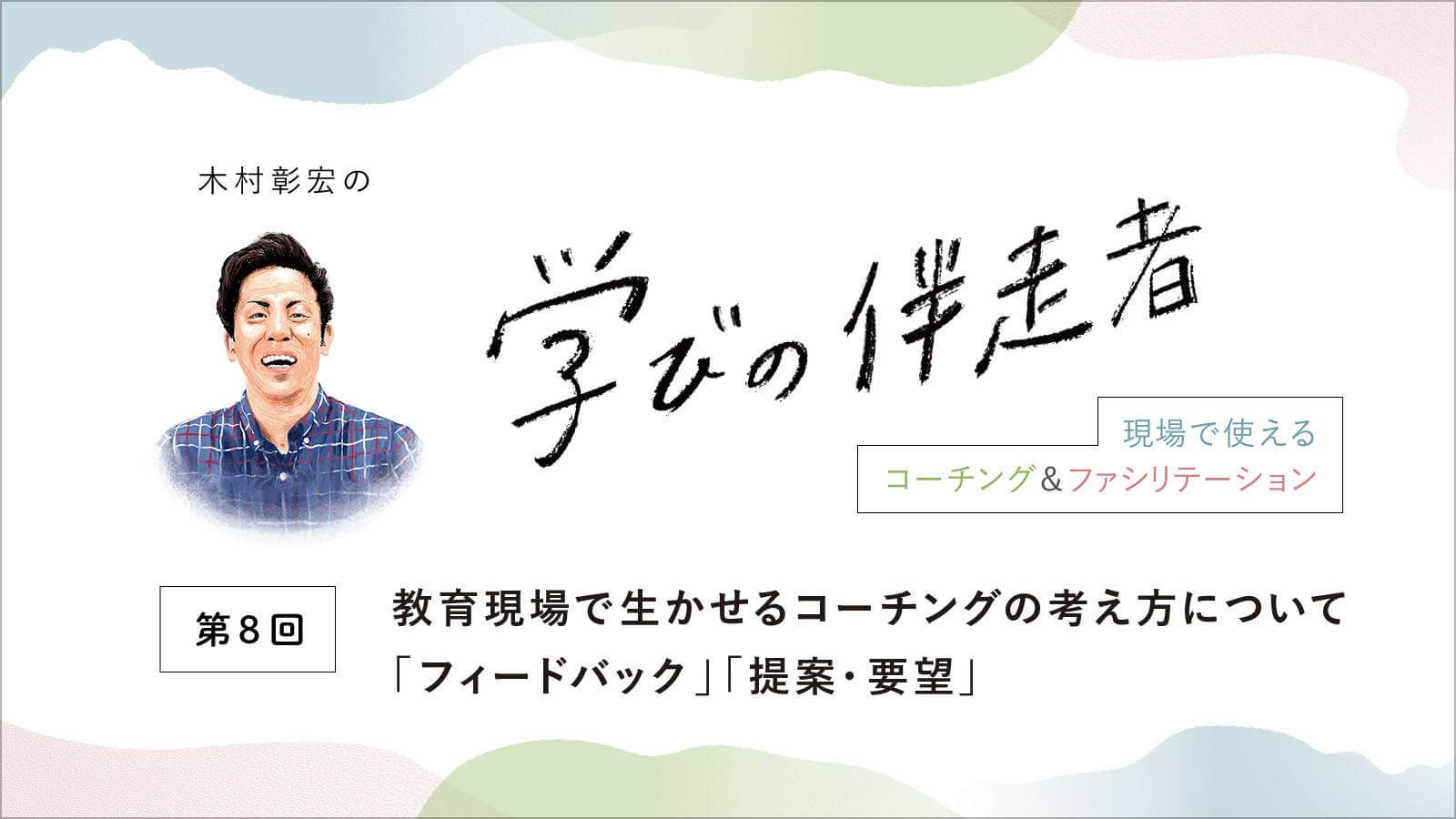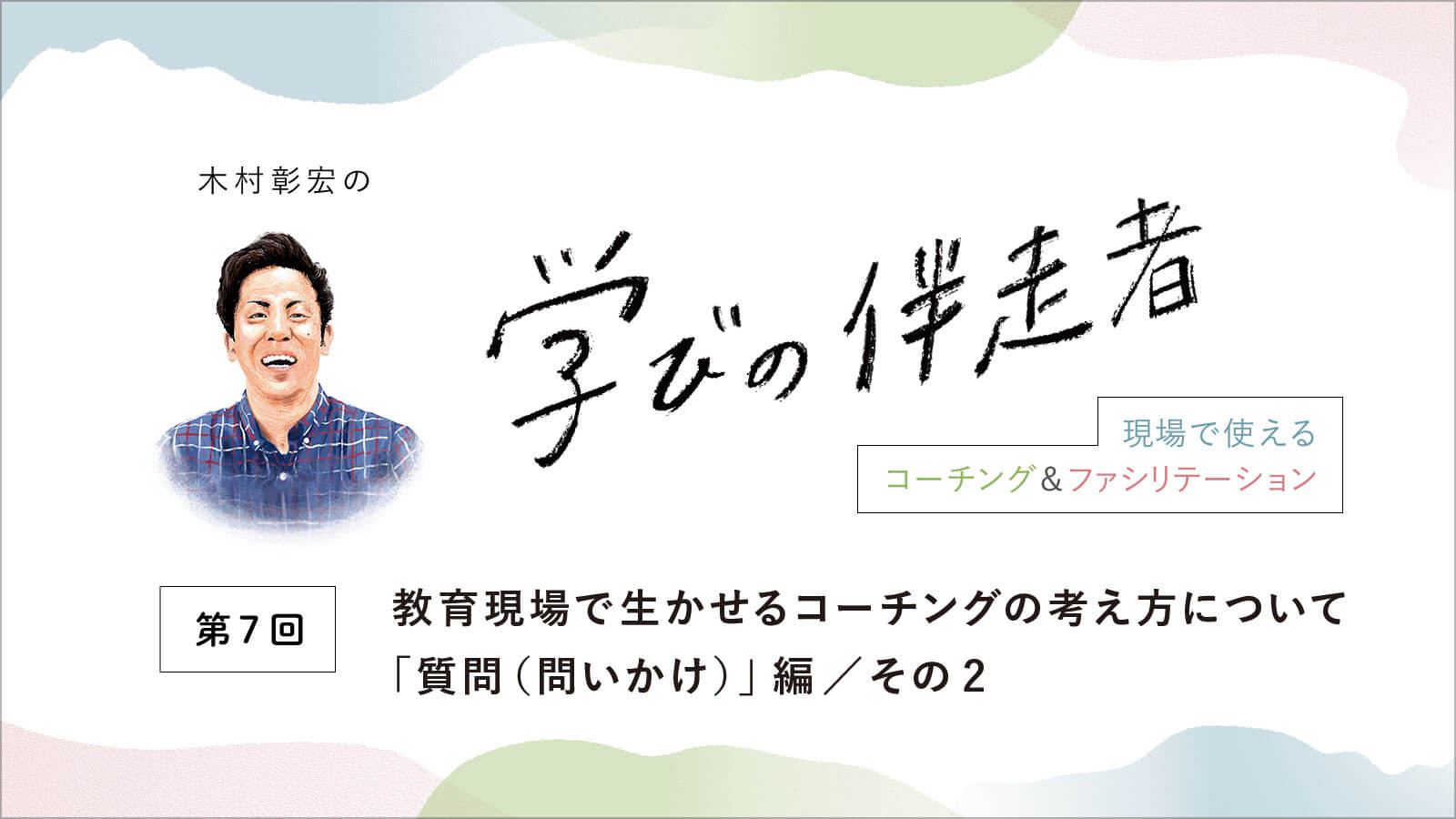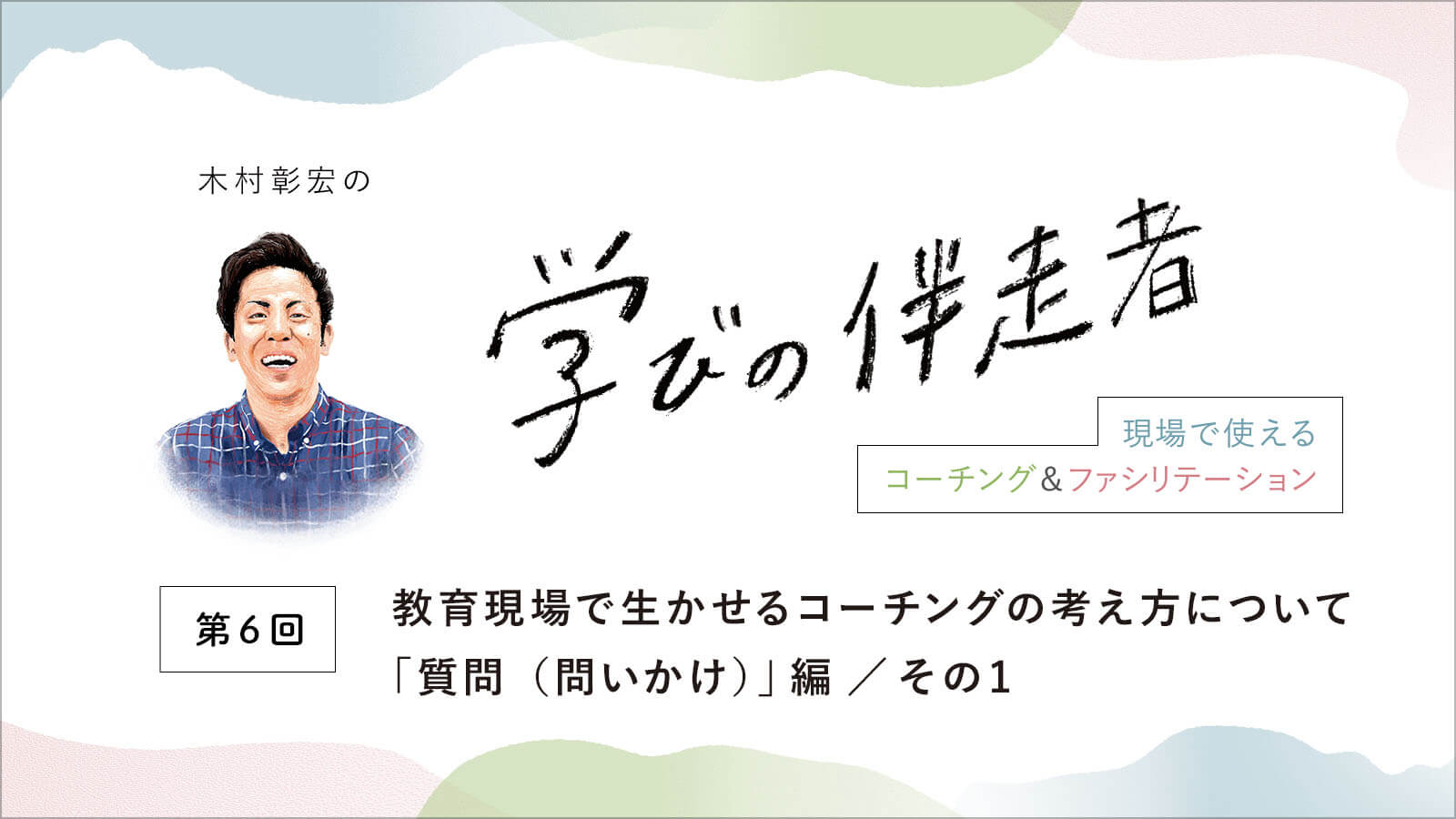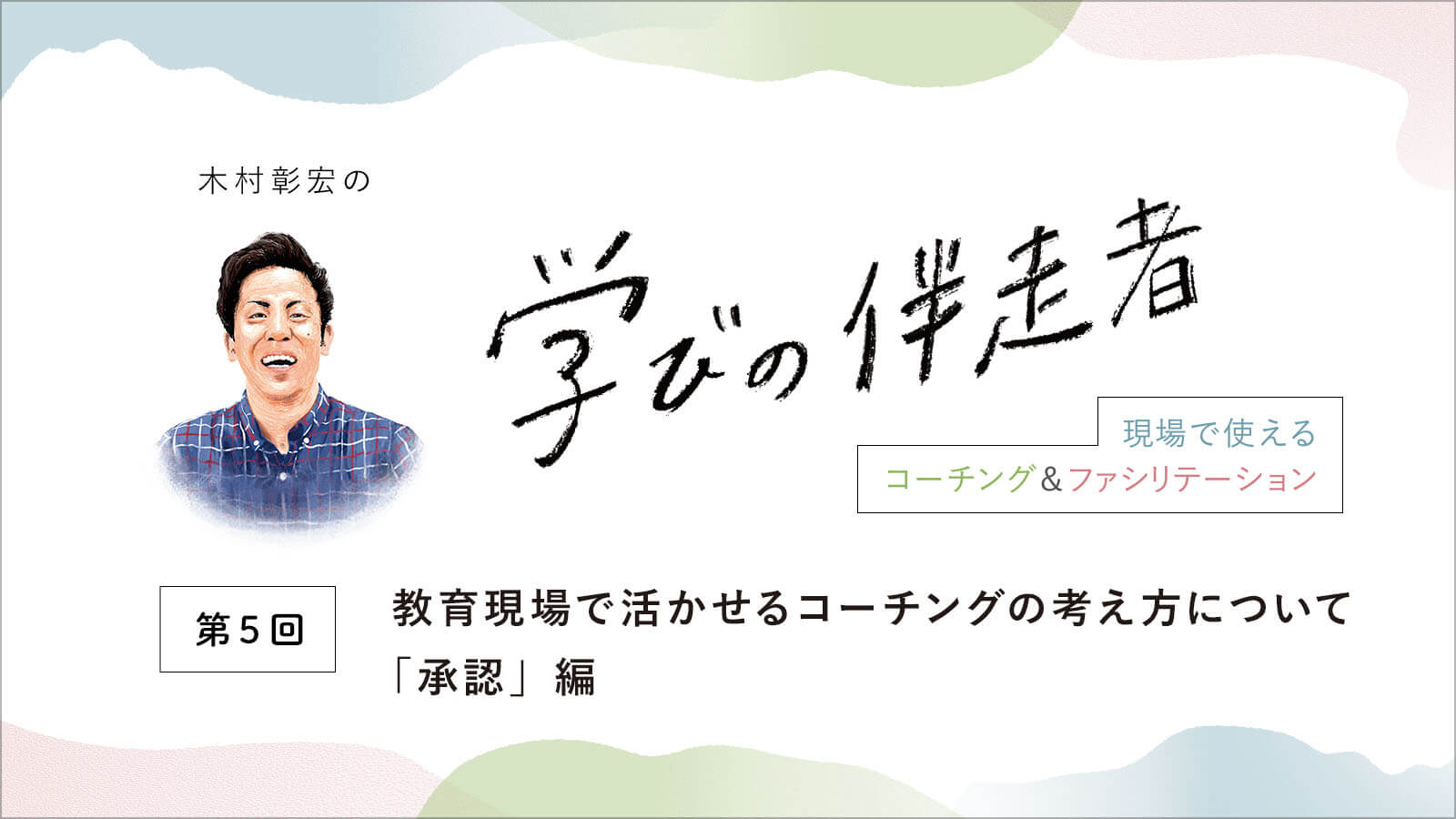【第13回】「プロジェクトアドベンチャー」を切り口に、ファシリテーションについて考える
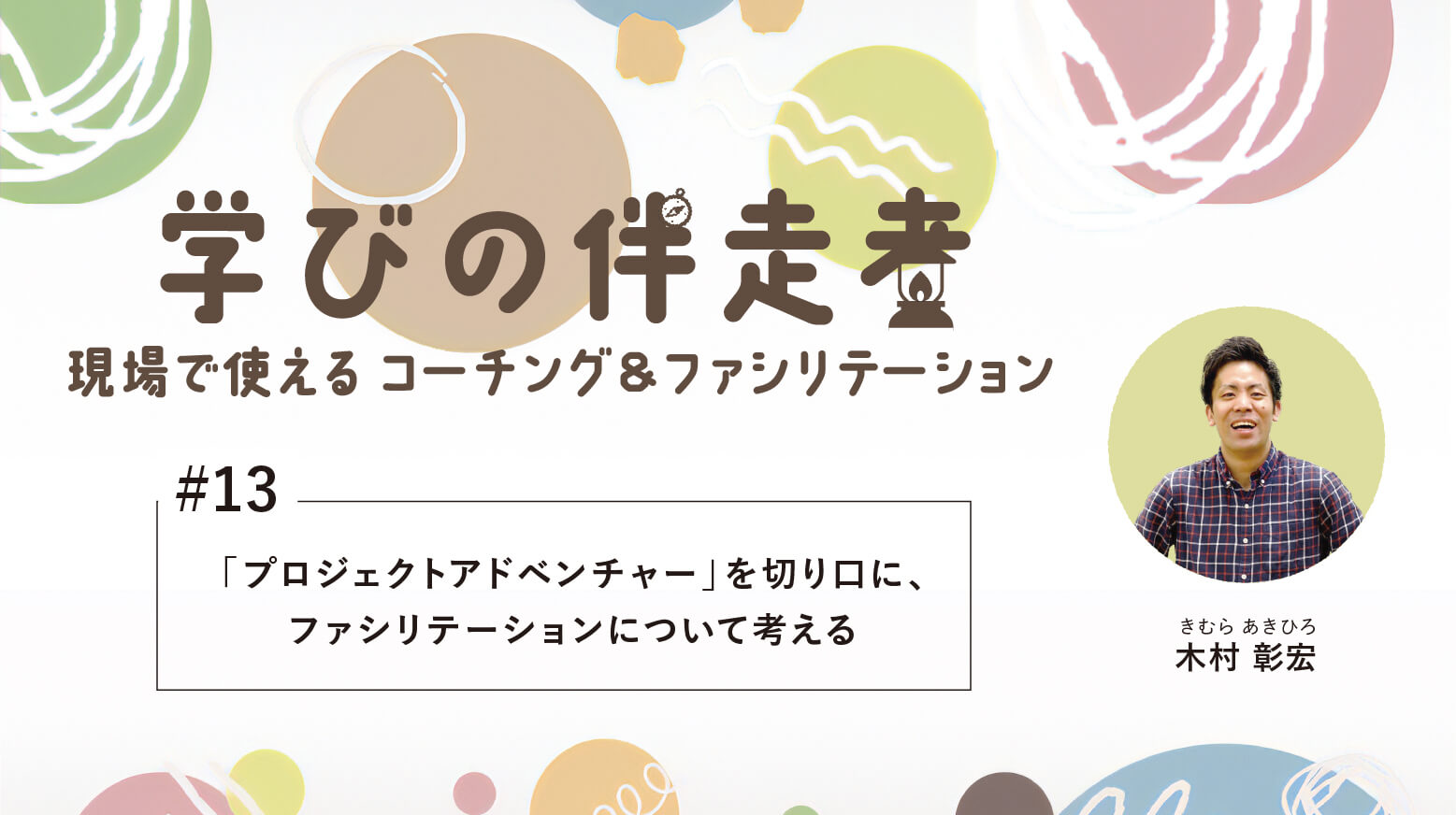
なぜ今、教育の世界で「コーチング」や「ファシリテーション」が注目されているのか?
伴走者として、学び手に関わる方々が、学び手の主体的・対話的な学びを加速させるために有効なコーチング(的な関わり)や、ファシリテーションスキルを紹介する連載です。

復興支援NPO職員、小学校の教師というキャリアの後、株式会社LITALICOに入社してLITALICOジュニア事業部にて子どもたちの発達支援に関わる。その後、人材開発部にて福祉・教育に興味関心ある学生や社会人のキャリア支援に従事。2020年4月から、コーチングを通じて起業家や経営者をサポートする株式会社コーチェットに参加し、トレーナー兼コーチとして活動。2021年4月からは、軽井沢風越学園に参画し、立ち上げ期の学校に関わる。2024年4月から「人と組織のコンサルティングファーム」株式会社MIMIGURIへジョイン。その他、複業として、プロコーチとしての業務、研修・WS設計、ファシリテーション業務、キャリア教育、教員の伴走支援などさまざまな活動を行っている。
この連載では、支援者・伴走者として学び手に関わる方々が、学び手の主体的・対話的な学びを加速させるための手段として活用できる、コーチング的な関わりやファシリテーションに関連する知識を紹介します。
さて、今回は「プロジェクトアドベンチャー」の、教育現場での活用を切り口に、ファシリテーションについて考えたいと思います。
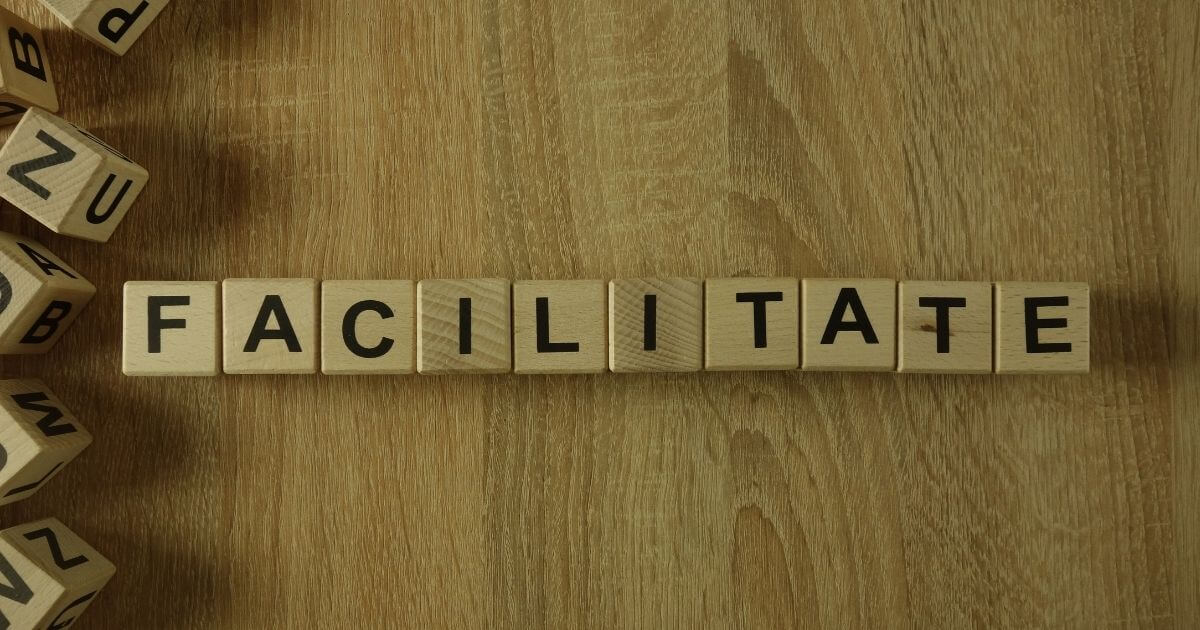
教育に関わっていらっしゃる皆さまであれば「プロジェクトアドベンチャー」(以下、PAと省略)という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。耳にしたことがある方は、PAに対してどんなイメージを持っていらっしゃるでしょうか?
ご存じない方は、ぜひ調べてみてください。日本にPAを普及させたProject Adventure Japanのホームページ含め、ネット上にもさまざまな情報がありますし、教育関係者向けの書籍等も販売されています。
日本にPAを普及させたProject Adventure Japanにファシリテーターとして関わらせていただいていることもあり、学校教育関係者などにPAの研修をご依頼いただくのですが、講師としてうかがった際に皆さまから、以下のように口々の印象を耳にします。
「クラスでやるゲームみたいなやつですよね」「いろいろな種類があるアクティビティですよね」「アクティビティを通していろんな人と関わらないといけない活動ですよね、あれ苦手だったな…」etc…
確かにPAのプログラムは、ジャンケンを活用したアクティビティや、チームで協力をしてパイプを使ってボールを運ぶチャレンジ、目隠しをして障害物の中を歩く活動など(これらはほんの一例です)と、活動自体のインパクトが大きく、それ故に「楽しいゲーム」「いろいろな種類があるアクティビティ」「強制的に参加させられる活動…」などと一側面のみが捉えられることが多いように感じます。
そのように捉えられがちなPAのルーツを少し説明してみると、もともとは1941年にイギリスで発祥したアウトワード・バウンド・スクール(OBS)という主に自然を舞台とした非営利の冒険教育機関から派生して生まれたプログラムが背景にあります。

「自然の中で、経験を通して学ぶアウトワード・バウンド・スクールのエッセンスを学校教育に生かせないか」と考えたアメリカの高校の校長などによって形になり、日本には1995年に普及して、そこから日本の学校教育や企業研修などに展開されていきました。
(1)【フルバリュー コントラクト】Full Value Contract(お互いの努力を最大限に評価するという約束)
(2)【チャレンジ バイ チョイス】Challenge By Choice(PAプログラムには強制がなく、挑戦への選択の自由が常に保証されている)
(3)【体験学習サイクル】Experiential Learning Cycle(体験からの学びを大切にする)
といった考え方が大切にしたい価値観として中心に置かれています。そんなPAの定義を、Project Adventure Japanは、ホームページにおいて、以下のように紹介しています。(2024年12月30日現在)
「プロジェクトアドベンチャー(PA)は、アドベンチャー体験から学ぶ、アクティブラーニングプログラムです。クラスやグループで課題解決や皆で楽しめる活動を行います。そして、体験⇄ふりかえりを繰り返して、学び手が主体的に学びを作っていくことを支援します。」

と、ここまで読んでくださった皆さまは、「PAとは何か」の輪郭が少しだけ見えてきたのではないでしょうか。少なくとも冒頭のコメントのような見え方は1つの側面でしかないとご理解いただけるはずです。
PAを教育現場で活用しようと試みられている方々に、私からよくお伝えしているのは、「PAは1つのアプローチ、1つの手段でしかない。結局、PAを活用して子どもたちと自分、子どもたち同士の間にどんな体験をつくっていきたいか。そしてその先に、どんな授業や学級、子どもたちのコミュニティをつくっていきたいか。それが子どもたちのどんな力を育むことにどうつながっているのか。そのために、どうファシリテーションをし、どう日常との整合性をとっていくかが大切だ」ということです。
例えば学級で30〜40分でできるPAのアクティビティを実施する場合、
・最初にどんな風にPAを子どもたちに紹介するか?
・長期スパンで見たときにどんな頻度・順番でPAに取り組むのか?
・なぜ学級でPAに取り組むかを子どもたちにどう説明するか?
・毎回のアクティビティを子どもたちにどのように手渡すか?
・子どもたちの体験(活動や話し合い、コンフリクト)にどこまで介入するか?
・参加しない子どもにはどのような声をかけるか?
・アクティビティを実施した後にどんな問いで振り返るか、何を問いかけるのか?
・PAの体験を日常にどう接続していくか?
などなど…丁寧に考えたいポイントは多くあります。

上記のように「PAという1つの手段を通して、子どもたちの集団をどうファシリテーションしていくか」という視点がないまま、PAのアクティビティをクラスで実施すると、ともすれば「活動あって学びなし」になりかねません。(もちろん、1つのレクリエーションとしては楽しいのですが)
また、「PAという手段を子どもたちの日常とどう紐付けるか、そのためにどのようにファシリテーターとして場や関わりの整合性をとっていくか」という視点がなければ、結果として子どもたちの失敗体験にもつながり、良かれと思って取り組んでいる活動が、逆におとなと子どもたちの信頼関係が損なわれるきっかけにもなりかねません。
具体的な失敗例を挙げてみると、学級でPAのアクティビティを実施・ファシリテーションをする際には「PAはチャレンジ バイ チョイスだから、やるかやらないかは自分で決めていいよ」「体験から振り返ろう。正解はないよ、どんな気づきや学びがあった?」などと子どもたちに関わるのに、他の教科の時間になると急に「早くやりなさい!」と一方的な強制力を持たせてしまったり、「先生が言っていることが正解です!言うこと聞いて!」などと一方的に関わってしまうなどです。

学級での生活は本来全てが地続きははずなのに、教科や活動内容によって、おとなの都合で関わりが変わってしまっては、子どもたちから「先生、さっきと今で言っていることが違うじゃん…」「結局、先生が正解を持っているんでしょ」などと反感を買ってしまいかねません。
さらに、連載第11回、「非言語情報の活用について考える」にも書いたことですが、ファシリテーターとして場や関わりの整合性が取れているかどうかは、非言語のメッセージにも現れるでしょう。子どもたちに「参加するかどうかはあなたが決めたらいいよ」と言いつつ、明らかに取り組むことを強要するような雰囲気を出してしまったり、参加した子たちだけを賞賛するような雰囲気を出してしまったりなどです。
これはPAに限らず、教育現場で取り組まれているさまざまな実践やアプローチをファシリテーションする際に、共通することではないでしょうか。
・自分が取り組んでいる実践やアプローチは、そもそも何を目的に実施しているのか?
・その実践やアプローチは、自分が子どもたちとつくっていきたい関係性や、子ども同士の理想の関係性にどうつながっているか?
・子どもたち一人ひとりに育みたい力にどうつながっているか?
・そのために、自分がその実践やアプローチを通して子どもたちの集団をどのようにファシリテーションをしていくのか?
・そんなご自身のファシリテーションは、その実践やアプローチ以外の日常との整合性が取れているのか?
子どもたちの活動や学習をファシリテーションしていく立場として、皆さんは上記をどれぐらい意識、言語化しながら、日々の実践やアプローチを実施されてるでしょうか。ぜひ一度、考えてみてくださいませ。
本記事の内容が、変化が激しく未来が見通しにくい今の時代に、伴走者として学び手に関わっていらっしゃる皆さまにとって、学び手のより良い成長・発達・変容につながる一助となっていれば幸いです。
連載内容について何かご質問等ございましたら、いつでもX(旧Twitter)のアカウント(@1130kimura)や Instagramのアカウント(@akihiro113o)に DMにてご連絡くださいませ。
参考資料:
『クラスのちからを生かす 教室で実践するプロジェクトアドベンチャー』
『グループのちからを生かす:プロジェクトアドベンチャー入門 成長を支えるグループづくり』
『クラス全員がひとつになる学級ゲーム&アクティビティ100』
『Project Adventure Japanホームページ』