プロジェクト型学習は、生徒、先生、地域の大人を変える学び。地域と共にある学校をつくる、公立中学校の本気の挑戦「高梁未来学」

地域と共にある学校づくりを目指す岡山県高梁(たかはし)市立高梁中学校は、2020年から「高梁未来学」というプロジェクト型学習に取り組んでいる。
生徒、先生、そして地域全体を巻き込み、地域の課題発見から解決に向けたアクション提案・実行までの一連の学びを中学校の3年間で系統的に学ぶことが特徴だという。
2020年度より始まり今年で5年目を迎えた高梁未来学を通して、生徒たちは地域社会に積極的に関わり、自分の将来を見据える力を養っている。同時に、先生や地域の大人たちも学びの場に参加し、互いに刺激を受け合っているそうだ。
一体どのような取り組みなのか、同校校長の小野 雅子さんと、主幹教諭の南 隆仁さんに話を聞いた。
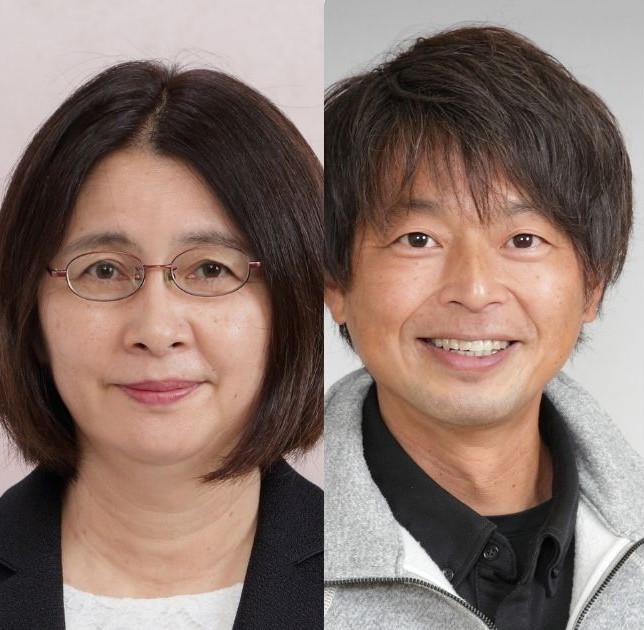
高梁市立高梁中学校 校長
南 隆仁(みなみ たかよし)さん【写真右】
高梁市立高梁中学校 主幹教諭
地域と協働する中で、地域の未来と自分の生き方について考える
——まずは高梁中学校について簡単に教えていただけますか?

高梁中学校は岡山県中西部に位置する、全校生徒277人・各学年3クラスという中規模校です。農村部ではありますが、市街地にも近いことから地域に出て活動しやすい立地に位置しています。
本校は学校目標に「未来を拓く生徒 心豊かな生徒 主体的、創造的に生きぬく生徒を育成する」を掲げ、生徒も先生も自ら考え、協働して活動することを目指して教育活動を行っています。
——貴校は、2020年から「高梁未来学」と呼ばれるプロジェクト型学習に取り組んでいるそうですね。どのような取り組みなのでしょうか?
高梁未来学とは、本校の総合的な学習の時間を使って取り組んでいるプロジェクト型学習の名称です。
この学習では、生徒が教科などを通して学んだことや、学校生活で身につけた力を生かしながら、地域を学習のフィールドとして、地域と協働しながら課題を探し、解決していくというもの。その過程で地域の未来と自分の将来や生き方について考えることを狙いとしています。

3年間のカリキュラムが系統的に組まれていることが特徴で、1年生では「発見高梁スピリット」として、地域の発展のために活動している人々や活動について「知り」、取材したことを動画やパンフレットなどにまとめて「伝える」ことを中心に学習します。
2年生では「高梁ジョブリサーチ」として地域をフィールドに職場探究学習を行い、仕事を体験・探究します。職場探究学習を通して働く意義ややりがいを実感すると共に、自ら設定した課題に対する答えを体験や大人との出会いの中で見つけ出し、最後は自分なりの考えを発表します。
そして3年生では「地域貢献プロジェクト」として、地域の課題に向き合い、その解決に取り組みます。地域と協働しながら課題に対する情報を収集・分析し、解決に向けた提案や活動を行っていきます。
——どのプロジェクトでも、自分たちが考えたことをまとめて発表・実行する点が特徴なのですね。
プロジェクトを通して、大人の前でも自分の意見を堂々と伝えられるようになることを目指しているんです。
ですので、1年生のうちからマインドマップなど考えを可視化するための思考ツールに触れて自分たちの学んだことを整理したり、プレゼンテーションや動画編集など、発表や発信に必要なスキルも学んでいくような設計にしています。
実際に3年生になると、コツコツと学んできたことの成果を発表するだけでなく、自主活動として地域に生かす挑戦につなげている生徒もいるんですよ。

自ら動き出す生徒たち、それを見て変わる先生たち
——そもそもなぜ高梁未来学は生まれたのでしょうか?
高梁未来学が始まる前、本校の総合的な学習の時間は、1年生は「ふるさと学習」、2年生は「職場体験学習」、3年生は「平和学習」と、独立した形で行われていました。
それをさらに発展させ、これからの社会を生きるために必要な“自立する力”を子どもたちに養うためにもっと地域をフィールドにした「開かれた学校づくり」、さらには「地域とともにある学校」を目指したいという提案が前校長からありました。
過疎化が進むこの地域では、子どもたちを大事にすることはもちろん、子どもたちにも地元・高梁を愛してほしいというのが共通の願いです。
また、今の時代を生きていく上では、自ら課題を発見して解決策を考え、実行していく力が必要不可欠です。そうした力を育てていける一番の方法は、やはり自分たちが住む地域と連携した教育活動を展開することではないか。
地域を見つめ、課題を発見し、自分に何ができるかを考えて地域の方々と協働して課題解決に取り組む。そうしたプロジェクト型の学びが、地域への貢献心と社会を生き抜く力を育てることにつながるはずだ。そんな考えから、高梁未来学は生まれました。
——その後どのように展開されていったのですか?

2020年のスタート当初は、3年生の総合的な学習の時間を担当する教員が生徒と一緒に「地域貢献プロジェクト」を立ち上げ、青年会議所や観光協会、ケーブルテレビ局など、地域の12団体と連携し、合計19のプロジェクトに取り組みました。
例えば、地元のバス会社と協力して路線バスの利用促進を図るプロジェクトや、地域の牧場と連携して地元産の牛肉を広めるプロジェクトを実施しました。しかし、その過程で、生徒たちに目標とする力をつけるためには、多くの授業時間を要するという課題も浮き彫りになったんです。

地域貢献プロジェクトの最終目標は、子どもたちが大人と肩を並べて自分たちの考えを堂々と理論立てて表現できる力を養うことでした。
そのためには、3年生の1年間だけでは不十分で、もっと1年生から思考ツールを活用して考えを整理したり、動画編集などのアウトプット手法を学んだりしながら、系統的な学びを積み上げる必要があると感じました。
そこで、3年生で最終的にどんなスキルを身につけてほしいのかを見据え、1年生から系統立てた学びを積み上げていける3年間を通じた全体像を整理した上で、その翌年に高梁未来学を全校での取り組みへと広げていきました。
——プロジェクト型の学びについて、生徒たちはどのような反応でしたか?
生徒たちや、彼らと連携してくださった地域の方々に取ったアンケートでは、最初は「成功するか不安」「イメージができない」という反応でした。
しかし次第に、「取り組んでみて、こういう活動が好きだと気づいた」「やりがいがあって達成感を感じた」という感想に変わっていきました。
中には「地域の課題を解決するために、中学生にできることは想像以上にたくさんあると感じた。ぜひ後輩たちにもこの気持ちを体感してほしい」と書く生徒も現れ、この感想には私も驚かされましたね。

——素敵な感想ですね。生徒の成長を感じた印象的なエピソードがあれば教えてください。
高梁未来学が5年目を迎えて、だんだんと私の知らないところでさまざまなプロジェクトが生まれ始めていることに、とても驚いています。
私が3年前に着任したときは「あんなことしてるな、こんなことしてるな」と把握ができたんですね。
でも次第に「〇〇さんが今度行われる地域のイベントで発表するらしいですよ」とか、地域の方から「今度やる地域のお祭りに生徒さんが手伝いに来てくれることになりました。ありがとうございます!」と言われることが多くなって。
子どもたちが自らチャレンジしている場面がたくさん生まれていることに、驚きとうれしさを感じています。

今年の中学3年生が、授業とは全く関係のないところで「廃園になった母校の幼稚園の跡地を使って、卒園した子どもたちの思い出になるような親子イベントを企画したい」と企画書を作って市に掛け合いに行っていました。
彼らの姿から、高梁未来学という学びが生徒の成長に大きな影響を与えているという成果を実感しています。
学校の先生を飛び越えて、自分たちも地域に貢献できるんじゃないか?と動き始めている生徒がいるって凄いことですよね。地域とつながる喜びや価値に気づいてくれているのかなと。
特に従来型の学びでは活躍の場面が少なかった生徒が、一生懸命自分で動き始めている姿を見ると、すごく変わったなと思います。
——そのような生徒の姿を見て、先生たちも感化されることがあるかもしれませんね。
そうですね。
子どもの姿には、大人も突き動かされる力があると感じています。実際に、私自身が高梁未来学を通して大きく刺激を受け、変わりました。
私の想像以上に地域での活動をとても楽しみ、やりがいを感じているように映る生徒たちを見ていると、私自身も自分の住んでいる地域で未来学をしてみたいなと思うようになりましたね。
当初この取り組みに「教科の指導が疎かになる」と抵抗感を抱く先生もいたのですが、生徒が変化する様子を見て、徐々にその先生も一緒に未来学を楽しむようになっていきました。
生徒の姿からこの取り組みの価値に気がついてくださったことが本当にうれしかったです。
地域と学校が協働するプロジェクト型の学びが、未来を拓く
——新しい取り組みを始めたとき、先生方にも負担があったのではないかと予想しますが、どのように解消されてきましたか?
「いい取り組みなのでどんどんやろう!」と進めてきた時期もありましたが、その中で「しんどい」と声をあげてくれた先生がいました。
そこで、総合的な学習の時間を担当する先生方が話し合って、カリキュラムのスリム化をしてくれたんですね。各学年で身につけてほしい力は何か、カリキュラムの中で重複している部分はないかを検討し、必要なものと不必要なものが整理できました。
そのような見直しの結果、先生方にとってこの取り組みが受け入れられやすい形になったと思います。
——地域との関わりはどのように深めていかれましたか?
本校では、地域向けに高梁未来学の説明会を実施しています。
地域の方と教職員が混じり合ってワークショップを行ったり、ゲストにお呼びした大学の先生から地域創生に関する講演を聞いたりするような場で、一昨年度から開催してきました。
今年の夏休みにも50人ほどの地域の方々と「中学校と地域の事業所が結びついたらどんなことができるか?」をテーマにブレインストーミングをして、アイデアを練り上げる研修を行いました。
参加した商工会議所の方からも、いい研修だったと評価していただき、子どものために集まったのに、いつの間にか大人の学びにもつながっていました。

こうした場を通じて地域の方々ともつながりが深まり、「今度中学校でこんなことさせてくれない?」と子どもたちの学びに協力してくださるようになりました。
高梁未来学を始めてから、生徒だけでなく、先生にも、地域の方にも大きな変化が起きたように感じています。
——生徒、先生、そして地域をも突き動かす高梁未来学に大きな可能性を感じます。お2人にとって、プロジェクト型学習とはどのような学びでしょうか?
本校の学校教育目標に「未来を拓く生徒」という言葉があるのですが、プロジェクト型学習は、自分で課題を見つけて探究して解決する生徒を育てるために、一番良い学びなのではないかと思っています。
そしてさらに地域社会とつながるプロジェクトには、自分が社会に出たときの姿を想像し、将来の可能性について具体的にイメージさせてくれる力があるとも感じています。
私は、生徒たちには「未来を拓く武器を集める学習だよ」と伝えていて。プロジェクト型学習が学びの土台になると、子どもが生き生きし始める。自分自身が若い頃に、こんな学校・学びがあったらいいなと思っていたものが、実際に形になった感覚があります。
高梁未来学で学ぶようなスキルやあり方は、教科学習はもちろん、社会に出たときにも役立ちます。最近だと、自己PR動画を作って面接にエントリーするといったように、自分を表現することが重要視されるようになりました。
そういう意味では、高梁未来学は特別なものではなく、現代の社会で必要なスキルを育むために、学校として必要な活動だと思っています。

ここまで話したように高梁未来学は、生徒が主体的に地域の課題解決に取り組むことで、学校だけでなく地域社会全体に変化をもたらしています。
また、教員や地域の大人も、生徒たちと一緒に取り組むことで自らの変容を実感しています。だから私は「地域に幸せを届ける学習であり、自分たちも幸せになれる学習」と捉え、生徒たちにもそう伝えています。
——最後に、読者へのメッセージをお願いします。

とにかく、子どもたちを型にはめたくないんです。子どもたちはいろんな可能性を持っています。それぞれの好きなことや得意なことがどこで花開くかは、学校だけで抱えるのはもったいない。学校の中だけで教育するのではなく、地域とつながることで、もっと広い場所で活躍できる可能性が広がります。
オンライン会議ができる今、地域に戻らなければ何もできないという時代も終わりました。どこにいても地域のためにできることを考えられたり、他の地域に行ったとしても、自分ごととして社会とつながる方法を見つけられる経験があれば、子どもたちの行動は変わってきます。
学校の教員だけでは伝えられないことがたくさんあるので、中学校の時期に、地域に限らずさまざまな分野で活躍している大人たちに会わせたいですね。そして、「大人になるのは悪いことじゃない」と、もっと子どもたちに伝えたい。高梁未来学は、そのための地域と連携したプロジェクト型の学びなのだと思っています。

以前、高梁未来学の地域向け説明会に参加してくださった市役所の方が「こんなに多くの業種の方たちが集まって話をする機会は、市でもほとんどない。ぜひこの中学校が核となり、地域の人々が集まり、地域のことを話す機会を大切にしてほしい」と言ってくださいました。
地域をまとめる役割として、もっと中学校が中心となってさまざまなことができるのではないかと感じていて、うれしかったですね。地域の方々も、子どもたちのためなら少々のことは気にせず集まってくださることも多く、非常にありがたいですし、いろんな企業の方たちも地域貢献について真剣に考えるのも良い流れだと思います。
地域と共にある学校として、今後も高梁未来学というプロジェクト型の学びを通して子どもたちの豊かな学習活動を盛り上げていきたいと思います。
〈取材・文:望月ゆかり、先生の学校編集部/写真:高梁市立高梁中学校 ご提供〉

![参加校の7割がリピートする、ユニクロ・ジーユー発!“届けよう、服のチカラ”プロジェクトとは!? [PR]](https://www.sensei-no-gakkou.com/wp-content/uploads/2024/03/3-2.jpg)